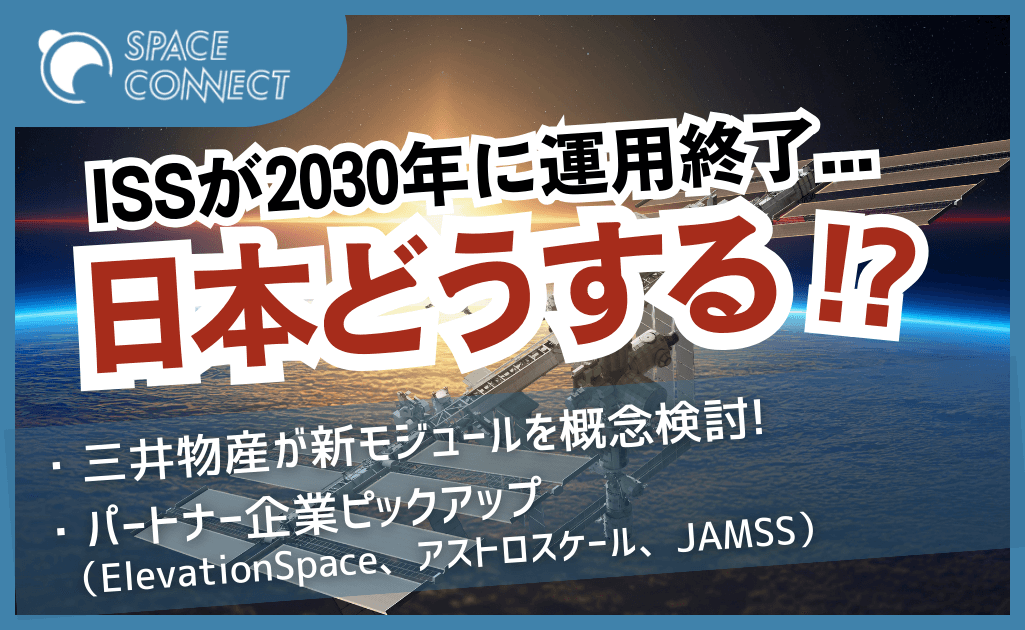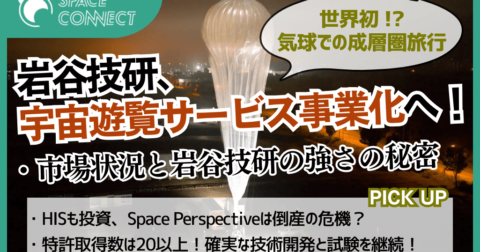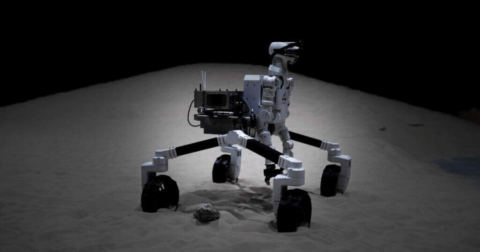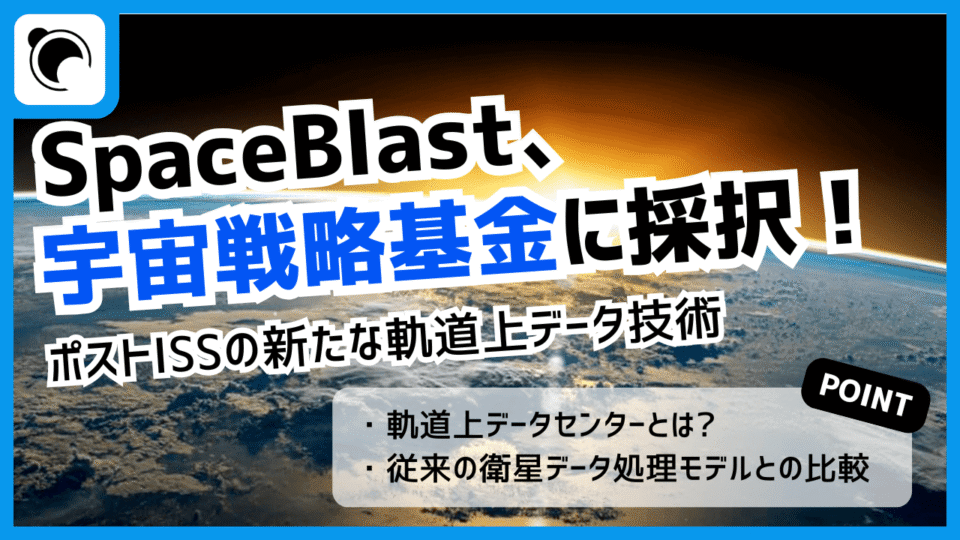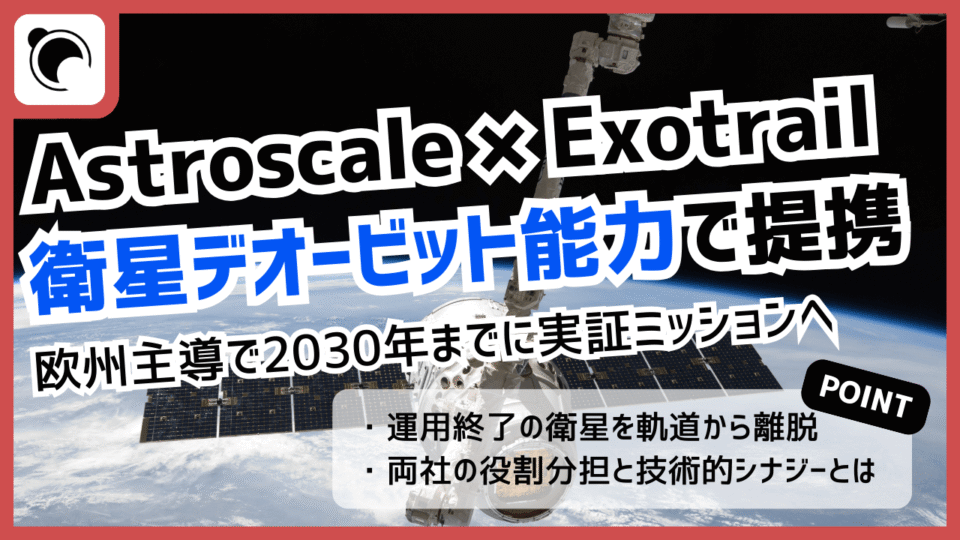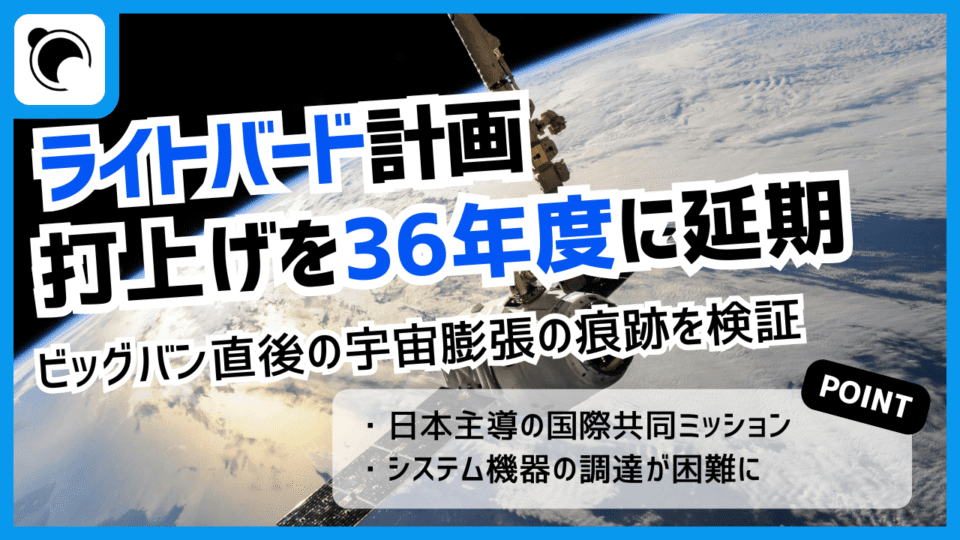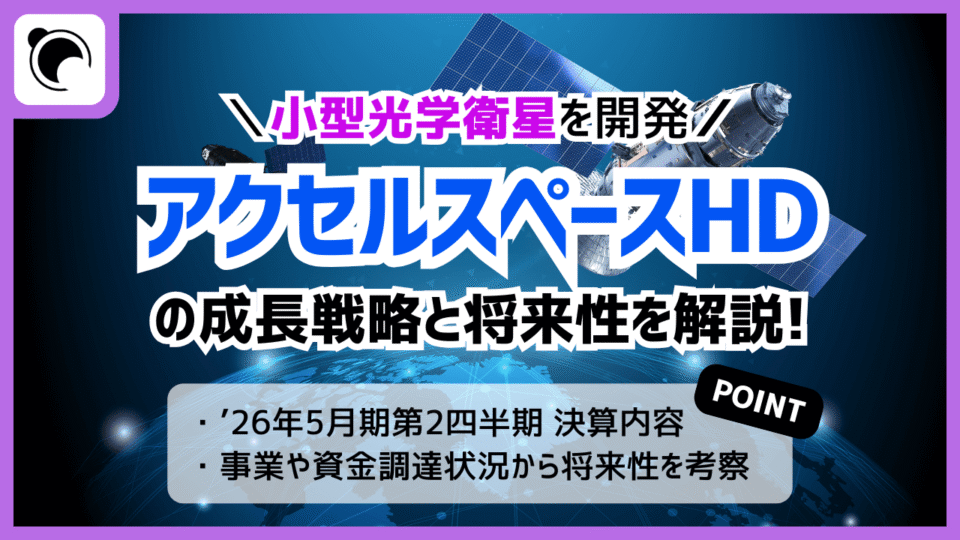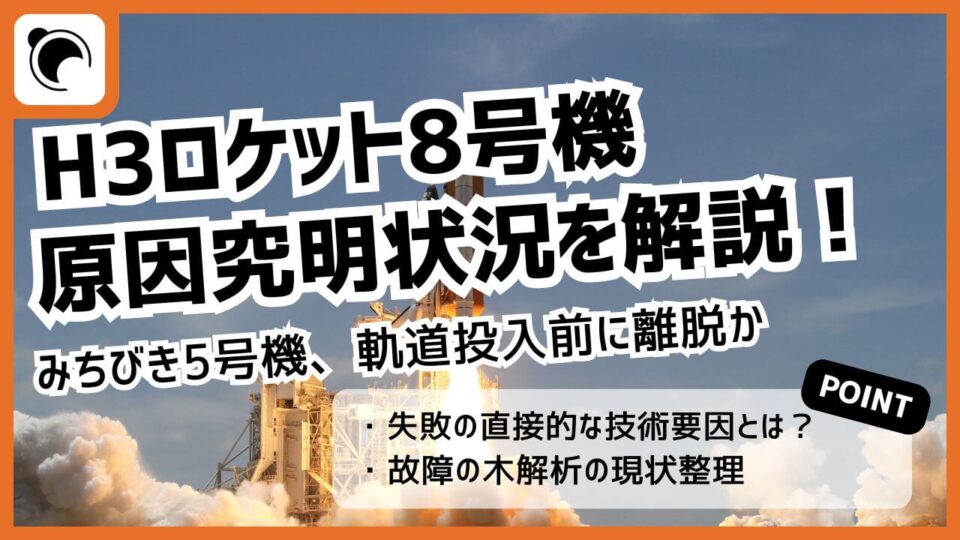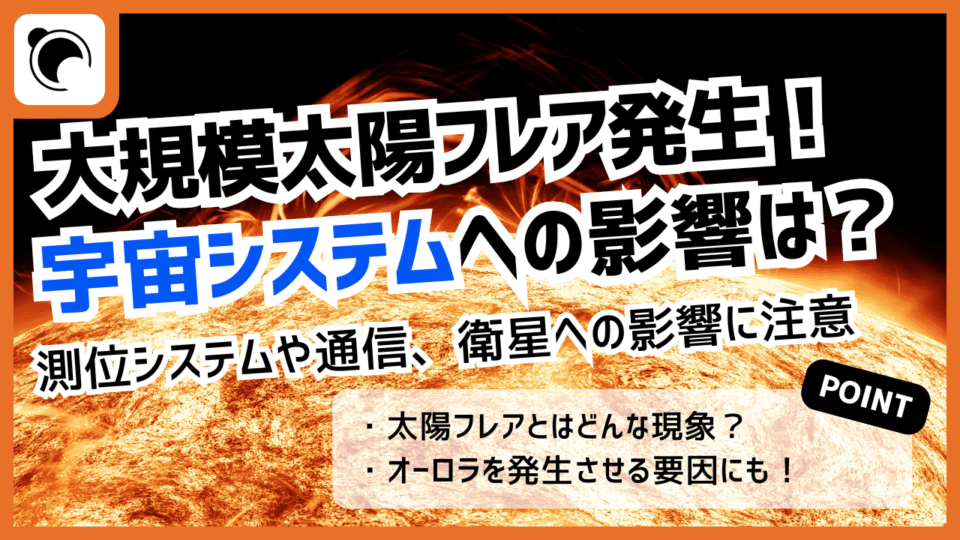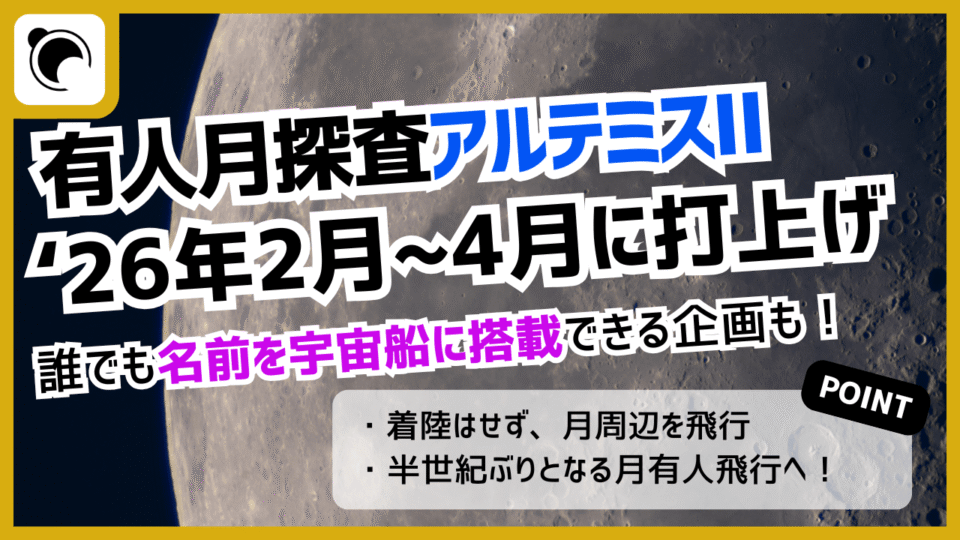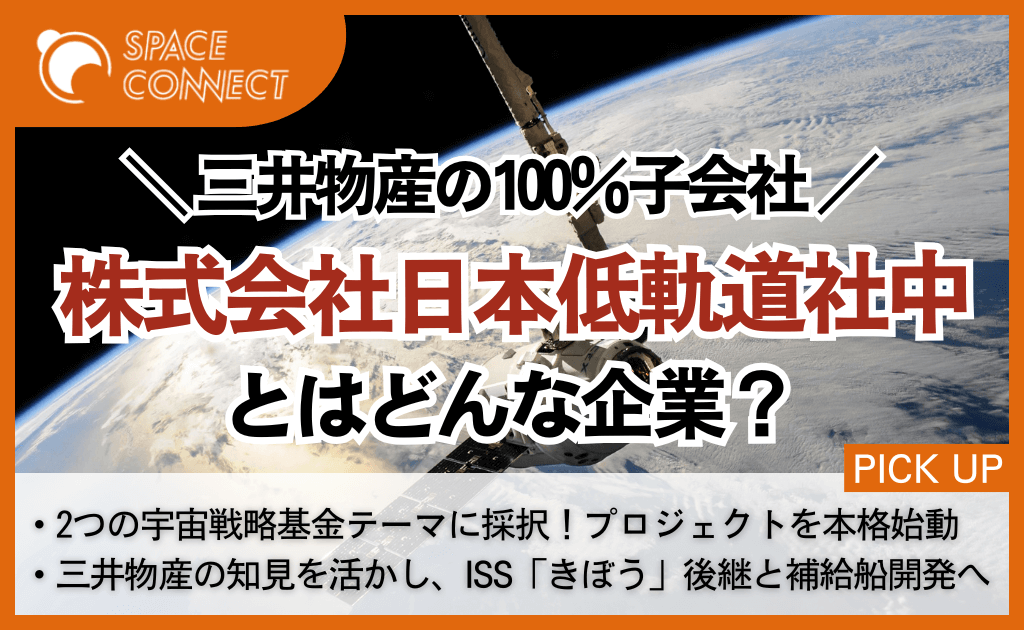
2025年7月28日、株式会社日本低軌道社中(以下、日本低軌道社中)は、宇宙戦略基金の支援対象として採択されたことを受け、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」モジュールの後継機にあたる「日本モジュール」および「商用物資補給船」の開発プロジェクトを本格的に始動したと発表した。
本記事では、日本低軌道社中の事業概要に加え、同社が宇宙戦略基金を通じて推進するプロジェクトの内容について紹介する。
目次
日本低軌道社中について
日本低軌道社中は、三井物産株式会社の100%子会社として2024年7月に設立された。
国際宇宙ステーション(ISS)が2030年に退役を迎えることを踏まえ、以後の日本の宇宙活動を民間の立場から支える存在として、国内外の宇宙業界から注目を集めている。
事業内容
同社は、ISS退役後の宇宙環境においても日本の宇宙ステーション利用を継続・発展させるため、「民間主導の宇宙利用インフラ」の構築を事業の中核に据えている。具体的には、以下の3領域を柱に開発を進めている。
- 宇宙ステーション用の新モジュールの開発
- 物資補給船の開発・運用
- 地球低軌道を活用した各種商用サービスの提供
これらの取り組みを通じて、微小重力や宇宙空間という極限環境を活かした医療・ライフサイエンス、新素材開発、高度データ処理、エンターテインメントといった分野での技術革新を促進し、地上産業との連携による新たな価値創出を目指している。
同社の強み
日本低軌道社中の最大の強みは、三井物産グループがこれまでに培ってきた宇宙事業における知見と実績を継承できる点にある。
三井物産は2018年、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟からの超小型衛星放出サービスの事業者として選定され、民間企業として打上げ機会の提供を開始した。
翌2019年には、子会社である三井物産エアロスペースが宇宙事業室を新設し、同サービスを引き継ぐかたちで事業を拡充。宇宙ステーション利用支援や衛星関連事業を展開し、低軌道空間におけるプレゼンスを高めてきた。
2023年には、三井物産がJAXAより「米国の民間宇宙ステーションに接続する日本モジュールのコンセプト設計事業」の実施事業者として選定されている。これにより、モジュールの設計仕様や開発スケジュール、コスト面の検討を主導する役割を担った。
これらの実績はすべて、日本低軌道社中の設立母体としての基盤を形成しており、同社は現在、ポストISS時代における日本の地球低軌道活動を牽引する民間プレイヤーとして、政府とも連携しながら次世代宇宙基盤の構築に取り組んでいる。
宇宙戦略基金で推進するモジュール・補給船開発
日本低軌道社中は現在、JAXAが主導する宇宙戦略基金[*1]において、以下2つの技術開発テーマに採択されている。
- 低軌道自律飛行型モジュールシステム技術
- 国際競争力と自立・自在性を有する物資補給システムに係る技術
これにより、ISS「きぼう」の後継となる日本独自の民間宇宙モジュールおよび、新型補給機HTV-Xをベースとした商用物資補給船の本格的な開発が始動している。
[*1]宇宙戦略基金:民間企業・大学等による複数年度にわたる宇宙分野の先端技術開発や技術実証、商業化を支援するために、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に設置された基金

① 日本モジュールの開発:自律飛行型モジュールシステム
1つ目のテーマは、低軌道自律飛行型モジュールシステム技術である。これは、自律的に飛行・運用できるフリーフライヤー型モジュールの設計・開発を目指すものである。
こうしたモジュールのニーズは、従来の宇宙ステーション内部における実験環境の制約に起因する。
たとえば、船内では常に人の活動や設備による微細な振動が発生しており、それが高精度な科学実験や材料製造に支障を及ぼすケースがある。また、機微な研究開発を国外拠点で行う際の情報流出リスクへの懸念も根強い。
これらの課題を踏まえ、日本低軌道社中は、自律的に運用可能でありつつ、海外の商業宇宙ステーションとの接続にも対応できるハイブリッド型モジュールの開発に着手。将来的には、複数年にわたる継続的な運用を想定している。
本開発を通じ、日本の民間企業が低軌道における宇宙環境利用を主導し、新たなビジネス創出と市場獲得を実現することが期待されている。
② 物資補給システムの開発:自立・自在な商用補給船
2つ目は、国際競争力と自立・自在性を有する物資補給システムに係る技術。このテーマでは、HTV(こうのとり)シリーズにより蓄積された輸送技術を基盤としつつ、民間主導による新たな商用補給システムの確立を目指す。
特に重視されるのは、「汎用性」と「柔軟性」である。
ISS退役後は、複数の商業宇宙ステーションが並行して稼働する可能性が高く、物資補給市場をリードするには異なるドッキング規格や輸送ニーズに対応可能な設計思想が不可欠となるからだ。
そこで、本補給システムでは、特に複数の商業宇宙ステーションへの柔軟な接近を可能とする高自由度の近傍通信・航法機能と、相対速度差の吸収や衝撃緩和に対応可能な、高い自律性・安全性・信頼性を備えた自動ドッキング技術の開発が中心となる。
これらにより、日本発の国際競争力を有する民間補給ソリューションの構築と、低軌道空間を活用した新たな商業ビジネスの展開が見込まれている。
さいごに
ポストISS時代の地球低軌道では、官から民への主導権移行が進み、数兆円規模の新たな市場が立ち上がろうとしている。各国が次なる拠点の確保を急ぐなか、日本低軌道社中の取り組みは、民間主導で宇宙インフラを築く先駆的な挑戦といえるだろう。
日本が低軌道経済圏において存在感を示せるかどうか。その試金石となるプロジェクトに、注目だ。
参考
宇宙戦略基金の交付決定を受け、ISS「きぼう」後継機の「日本モジュール」と「商用物資補給船」開発プロジェクトを本格始動(日本低軌道社中, 2025-07-31)
三井物産エアロスペース株式会社 公式HP(三井物産エアロスペース, 2025-07-31)