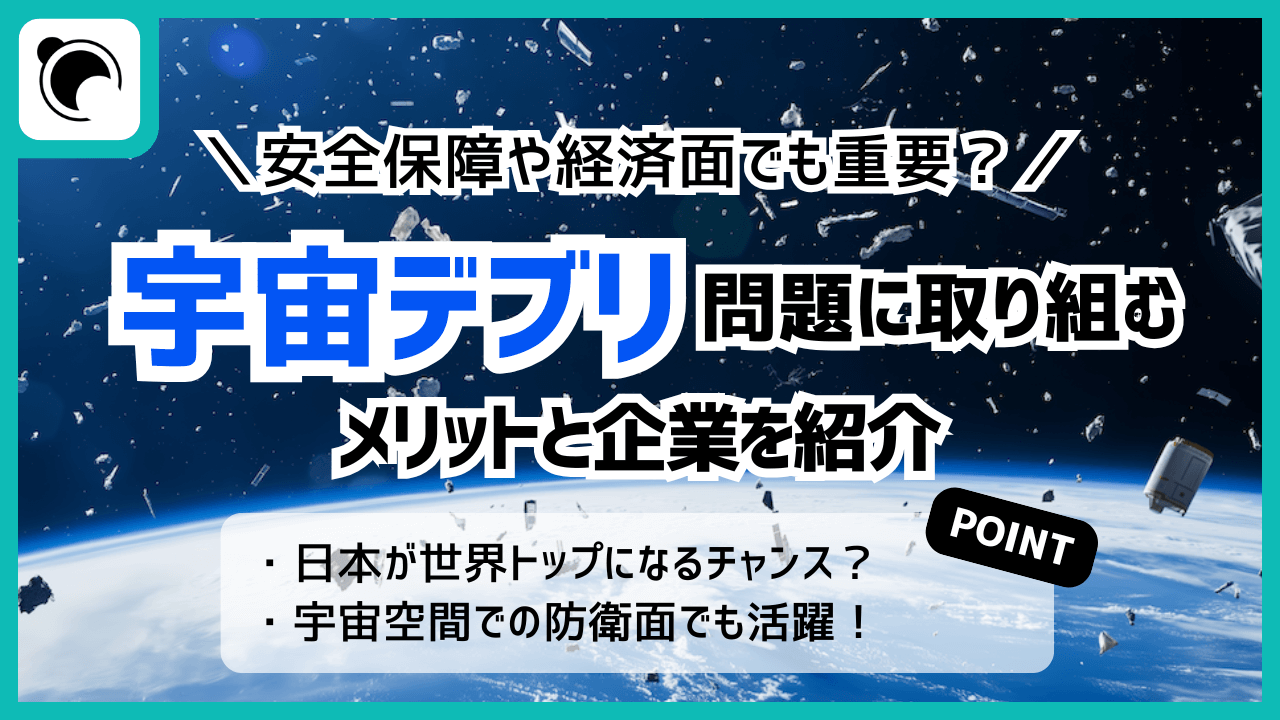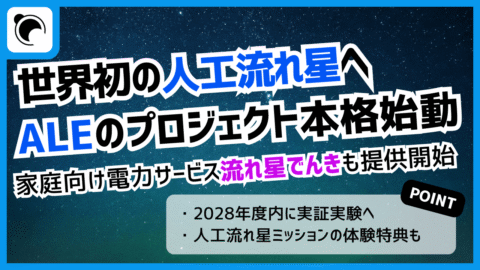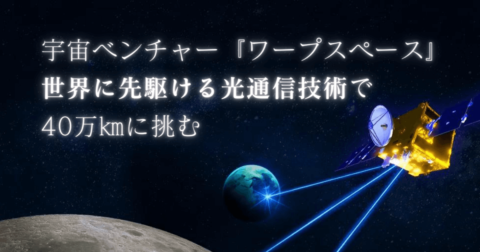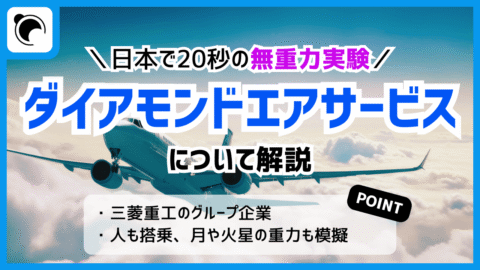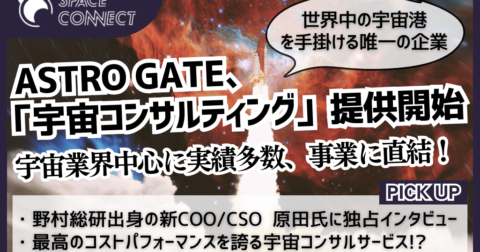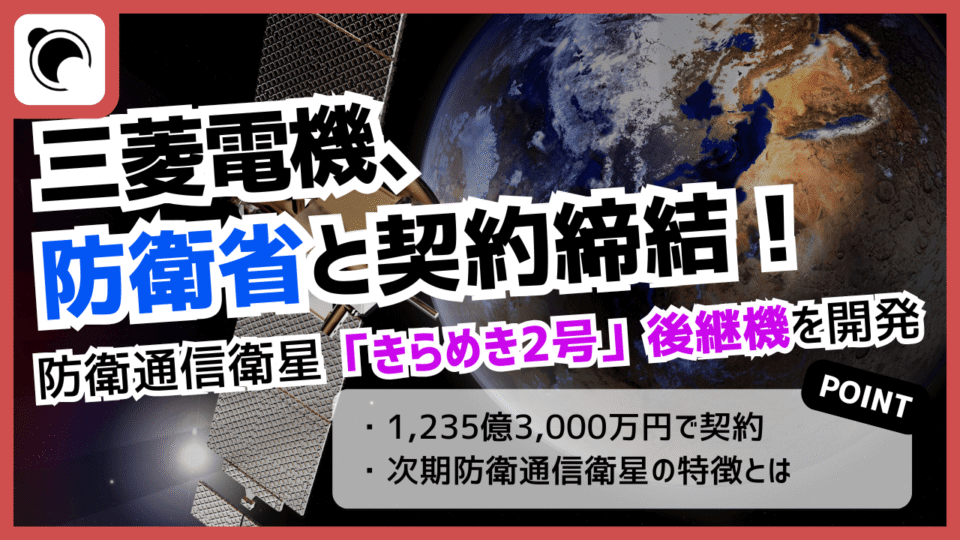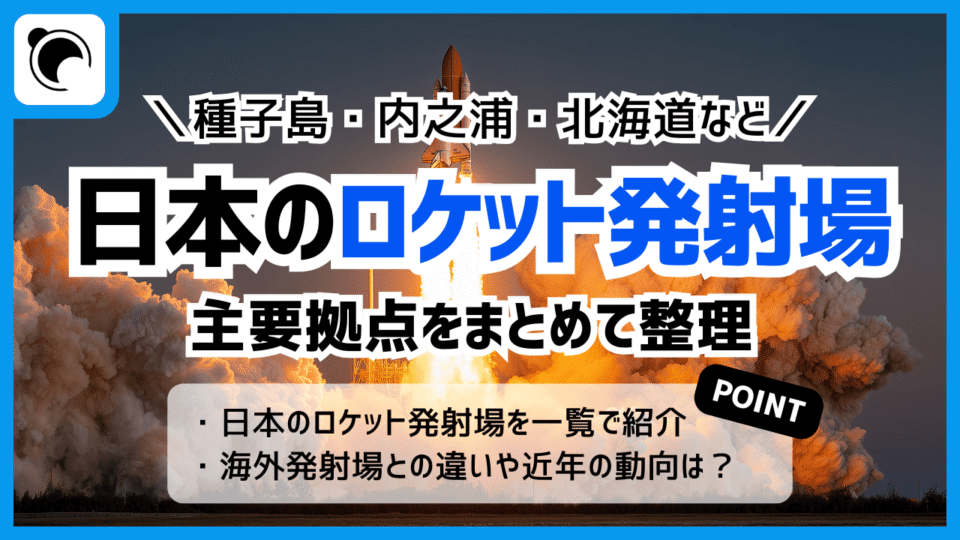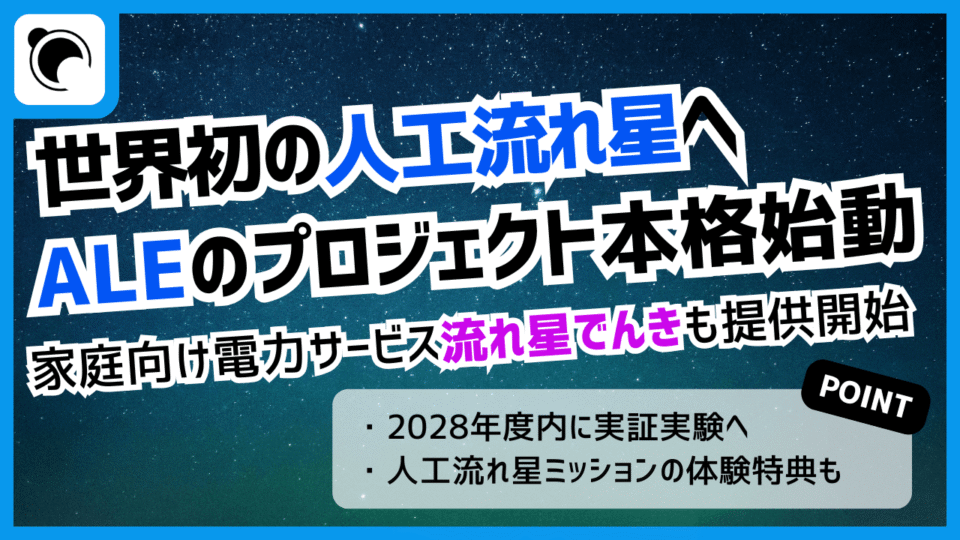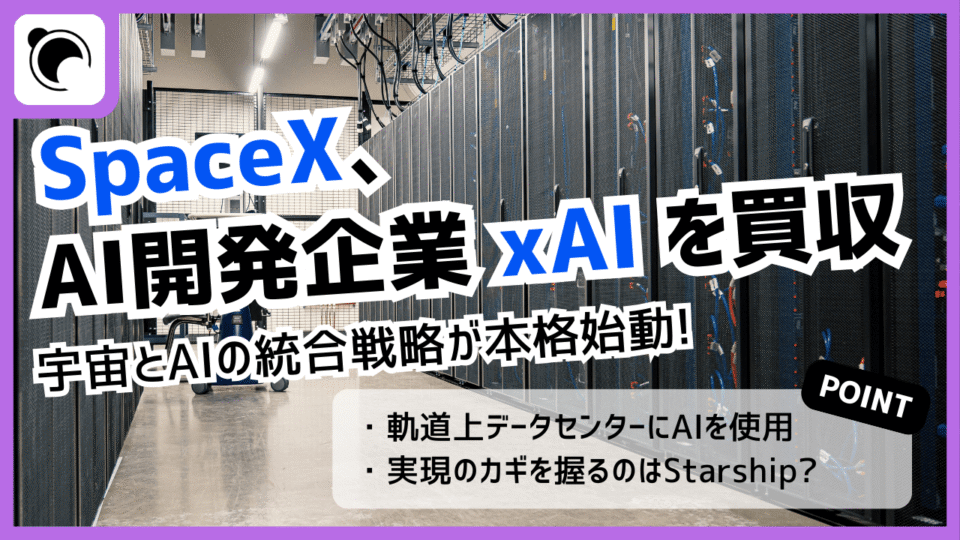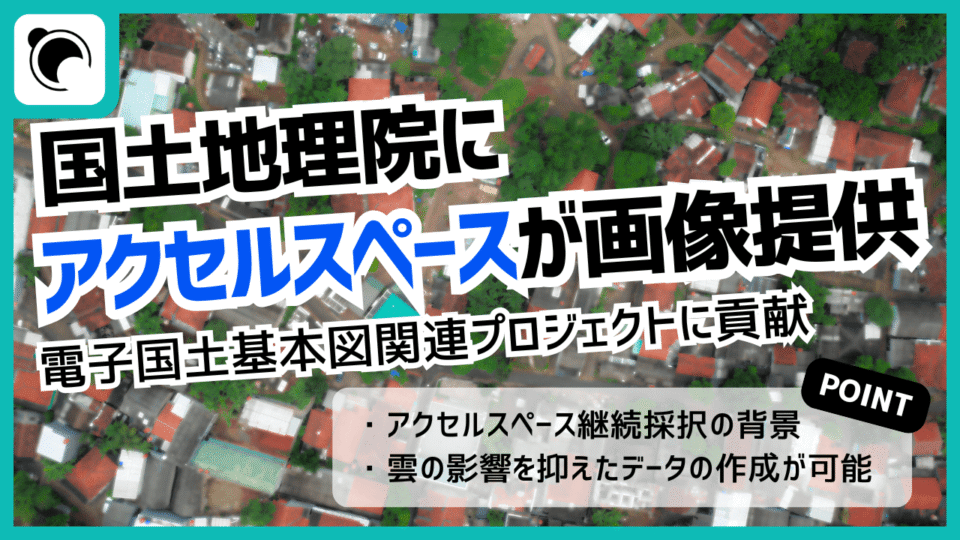近年、高度2,000㎞以下の地球低軌道(LEO)を中心に、通信衛星や地球観測衛星のコンステレーション展開など宇宙ビジネスの拡大が急速に進んでいる。
その一方で、人工衛星やロケット部品の破片などからなるスペースデブリ(宇宙ゴミ)も急激に増加しており、軌道上の安全確保が喫緊の課題である。この問題の解決に向けて、さまざまな企業や機関がスペースデブリの除去・対策技術の開発に取り組んでいる。
本記事では、スペースデブリの現状について言及するとともに、この課題の解決に取り組む2社:東証グロース市場に上場している宇宙ベンチャー 株式会社アストロスケールホールディングスと、スイス発の宇宙企業であるClearSpaceをピックアップし、事業内容や最近の注目トピックについてご紹介していく。
スペースデブリの脅威と社会への影響
スペースデブリの脅威
スペースデブリは、人工衛星や宇宙ステーションなどの軌道上の構造物と衝突するリスクを常に抱えている。 万が一衝突が起これば、衛星や宇宙船の機能喪失や破壊につながるだけでなく、新たなスペースデブリの発生によって状況がさらに悪化する恐れがある。
欧州宇宙機関(ESA)が発表した「宇宙環境レポート2025」によると、現在、地球周回軌道には約1万1,000基の稼働中の宇宙機に加え、宇宙監視ネットワークによって約3万個のスペースデブリが追跡されている。
さらに、追跡されていない小型のスペースデブリの存在もある。具体的には、直径1cm以上のデブリは120万個以上、10cm以上は5万個以上存在すると推定されている。
このような背景を受け、近年では新たに打ち上げるロケットや衛星がスペースデブリ化するのを防ぐ取り組みが活発化している。あらかじめ軌道離脱用のエンジンやその他の機構を搭載し、運用終了後には大気圏へ再突入させることで、軌道上に不要な物体を残さないようにするのだ。
このような動きは急増傾向にあり、2024年には初めて、制御された大気圏再突入の件数が制御されていない大気圏再突入の件数を上回ったという。
しかし、それでもなおスペースデブリの総量は増加し続けている。
現状のままでは、今後、新たな打ち上げを行わなかったとしても、既存のスペースデブリ同士やスペースデブリと宇宙機の衝突による破片増加が進み、大気圏再突入によるスペースデブリの減少数を上回る恐れがある。
こうした衝突連鎖が現実化すれば、将来的に一部の軌道を利用できなくなる可能性も指摘されているのだ。
もし宇宙インフラが止まったら?現代社会への深刻な影響
仮にスペースデブリの増加によって宇宙利用が制限された場合、その影響は社会や経済のあらゆる分野に及ぶ。
たとえば 、測位衛星による位置情報サービスが停止すれば、航路設定等に支障が生じることにより大規模な欠航や遅延が予想される。
また、測位衛星は時刻同期の基準としても使用されているため、ナノ秒単位の精度が求められる金融機関の株式・債券・為替取引や銀行間決済などでエラーや遅延、業務停止のリスクが高まる。
加えて、気象衛星による天気予報や地球観測衛星による災害対策などにも深刻な影響が及ぶ可能性もある。
デブリ削減のための「捕獲」技術
上記のような事態を解決するためには、新たなスペースデブリの発生を防ぐだけでなく、すでに存在するスペースデブリを積極的に除去する取り組みが不可欠だ。
デブリ除去の方法としては、高出力レーザーを照射してスペースデブリを減速させるなど、様々なアプローチが研究・開発されている。
その一つが、スペースデブリに近づいて直接捕獲する方法である。
これは、デブリ除去用衛星が制御不能となったスペースデブリに接近し、ロボットアームやネットなどを用いて把持、安全に軌道離脱や大気圏再突入を促す技術だ。
除去対象となるスペースデブリはほとんどが不規則な動きをしているため、衝突を避けながら近づき、安全に捕獲するための高度な誘導・追尾・接近制御が求められる。
また、直接捕獲技術の開発は以下のような他の軌道上サービスや宇宙安全保障への応用も期待されており、注目の技術であるのだ。
- 衛星の延命(給油・修理)や軌道投入の支援
- 将来的に不審な衛星や攻撃的な衛星に対する防御手段
デブリ捕獲技術を開発する注目企業と最近の動向
スペースデブリ除去に民間企業として世界で初めて本格的に取り組んだのが、日本のアストロスケール。 日本をはじめ、英国、 米国、イスラエルなどに子会社を設立し、デブリ除去の実証実験やサービス開発の先駆者として世界中の注目を集めてきた。
近年では、アストロスケールに続き、同様の分野に挑戦する民間企業も徐々に増えている。その代表格が、スイスのClearSpace(クリアスペース)だ。両社は競争関係にあり、国際的な注目を集めるプレイヤーである。
ここからは、それぞれの企業の概要と最新の動向について紹介する。
アストロスケール
アストロスケールは2013年の創業以来、デブリ化防止装置や既存デブリの除去など、スペースデブリ対策に関わる様々な技術の開発を手掛ける企業。長期に渡り安全で持続的な宇宙環境を目指すため、ビジネスモデルの確立や、複数の企業・団体・行政機関と協働して宇宙政策の策定などにも取り組んでいる。
同社はこれまで、様々な宇宙ミッションを実施し、軌道上サービス業界をけん引してきた。数多くの実績により、アストロスケールはデブリ除去技術の分野で世界をリードする存在となっているのである。
同社がこれまで実施してきたミッションと最近の動向は以下の通りだ。
欧州との連携によるデブリ除去ミッション
同社は2021年より、世界初の民間デブリ除去実証ミッション「ELSA-d」を実施。捕獲機構を備えたデブリ除去衛星と模擬デブリにより、デブリ除去に係る一連のコア技術を実証した。
この成果は欧州宇宙機関(ESA)、英国宇宙庁、衛星通信サービスを提供するOneWebとのパートナーシップで進められている「Sunrise(サンライズ)」プログラムのミッション「ELSA-M」にも活かされている。
「ELSA-M」はあらかじめドッキングプレートを備えた衛星を磁力を利用して捕獲するもので、2026年ごろの軌道上実証が予定されている。
さらに、アストロスケールは英国宇宙庁の支援のもと、英国のスペースデブリ2機を安全に除去するための研究プログラム「COSMIC」も進めている。2025年2月に、衛星の捕獲と軌道離脱に必要な技術のテストや技術改良を行うフェーズⅡの中間報告を完了している。
ClearSpaceも同様のミッションに採択されているが、打ち上げと低地球軌道(LEO)での運用に先立つ宇宙船の製造、組み立て、試験を行うフェーズⅢに進めるのは1社のみとされている。
日本政府・JAXAとの連携によるデブリ除去ミッション
国内では、2020年にJAXAの商業デブリ除去実証プログラム(CRD2)に選定され、2024年からミッション「ADRAS-J」を開始。
「ADRAS-J」は、実際のスペースデブリに安全に接近し、デブリの状況を調査する世界初の試みであり、2024年に世界初となるスペースデブリの周回観測を実現。さらにスペースデブリから約15mまで接近することにも成功しており、民間企業がデブリに対して近傍運用した例では、世界で最も近い距離となっている。
今後は、デブリ除去としてその捕獲や軌道離脱も実施する予定となっている。
また、2023年10月に文部科学省が推進するSBIR制度に同社が採択されたことから開始された、大型の衛星デブリを観測対象とする「ISSA-J1」のミッションでは、機体の基本設計や航法センサの開発が行われてきた。
そして2024年12月からは、詳細設計や衛星組立、地上試験、運用準備等が進められている。

デブリ除去以外の事業も展開
アストロスケールは、これまで獲得してきた衛星開発技術や宇宙空間における近傍運用技術を土台に、デブリ除去以外の事業も展開している。
2025年1月には、内閣府主導で創設された、経済安全保障上重要な技術を育成するプログラムに採択され、宇宙空間における燃料補給技術の確立に取り組んでいる。
この技術は、運用中の衛星に燃料を補給するものであり、衛星の寿命を延長させることができる。これにより、衛星機数や打ち上げ回数を低減することにつながるほか、燃料の量的な制約があると実行できないようなミッションも可能になる。
さらに、同年2月には防衛省より機動対応宇宙システム実証機の試作を受注している。
この実証機の目的は、各国が脅威を監視し敵を抑止する能力を向上させようとする中で、安全保障上有効となる技術を実証することにある。
将来の静止軌道上での宇宙物体の位置や軌道等に加え、宇宙機の運用・利用状況及びその意図や能力などを把握する宇宙監視、情報収集、宇宙作戦能力の向上に必要となる技術が搭載される。
高機動性、小型であること、そして光通信の実証も行うことが特徴であり、防衛省・航空自衛隊の宇宙監視能力の向上に期待できるのだ。

ClearSpace
ClearSpaceは2018年に設立されたスイスの宇宙企業。まだ宇宙実証は行われていないが、本格的なデブリ除去ミッションに挑戦している。
同社は、以下に紹介するミッション、他企業との契約等を通して、確実に技術開発を進めている。同社の事業や最近の主なトピックは以下の通りである。
ESAとの連携によるデブリ除去ミッション:ClearSpace-1
「ClearSpace-1」は、欧州宇宙機関(ESA)のデブリ除去プログラムであり、ClearSpaceはその主要事業者として注目されている。
同社は「ClearSpace-1」の契約を2019年に獲得。ロボットアームでスペースデブリを把持し、デブリ除去衛星とともに大気圏再突入・焼却させる計画となっている。
ClearSpace-1ミッションのターゲットであるスペースデブリは、2001年に打ち上げられた自律型運用を目的とするESAの小型人工衛星「PROBA-1」である。
このPROBA-1を除去するために、ClearSpace-1は、2026年後半以降にアリアンスペースのVega Cロケットにより打ち上げられる予定だ。
英国宇宙庁との連携による複数デブリ除去ミッション:CLEAR
ClearSpaceが進めるミッション「CLEAR」は、アストロスケールの「COSMIC」同様、英国宇宙庁との契約により進められる複数のデブリ除去ミッションである。
ClearSpaceは2025年5月に「CLEAR」のフェーズⅡを完了しており、英国初のデブリ除去ミッションにおける重要なマイルストーンを達成。
ロボット捕獲システムは機械的リスク軽減試験に合格し、厳しい打ち上げ時の負荷に耐えられることを証明。同時に、ClearSpaceが開発した画像処理アルゴリズムを現実的な環境でテストし、システムが宇宙デブリを正確に検出・追跡できることなどを実証した。
上述したように、このミッションではフェーズⅢに進めるのは1社のみであり、ClearSpaceはアストロスケールと競争関係にある。
デブリ除去以外の事業も展開
そして、ClearSpaceもまた、デブリ除去以外にも事業を広げている。
2024年1月には、軌道上燃料補給の新興企業であるOrbit Fabと提携を発表。
両社は協力して軌道上での燃料補給サービスを協力して進めていく予定で、サービスの顧客はOrbit Fabから燃料を購入し、ClearSpaceの宇宙機から燃料を受け取ることが可能になる。
両社は2026年ごろまでに、燃料補給プラットフォームを宇宙に打ち上げることを目標としている。
さらにClearSpaceは、2024年2月に英国宇宙庁と、燃料補給ミッションの実現可能性を調査するための契約も締結している。
さいごに
いかがでしたか。
宇宙ビジネスの拡大にともない、スペースデブリ問題への対応は「避けて通れないインフラ整備」として、世界中の政府・企業にとって喫緊の課題となっている。
この課題に最前線で挑むアストロスケールとClearSpaceは、いずれも世界を代表する存在だ。
ClearSpaceは、欧州宇宙機関(ESA)との契約をいち早く獲得し、アストロスケールは、模擬デブリを用いたELSA-dや、実際のスペースデブリに接近・周回飛行したADRAS-Jなど、実証フェーズを確実に積み重ねることで、技術開発を現実の成果として示してきた。
両社は競合関係にあるが、持続可能な宇宙環境の実現という大きな共通目的においては、むしろ協調が不可欠な存在といえるだろう。
宇宙という共有資源をいかに次世代に引き継ぐか――その挑戦の最前線を、今後もSPACE CONNECTでは追いかけていく。