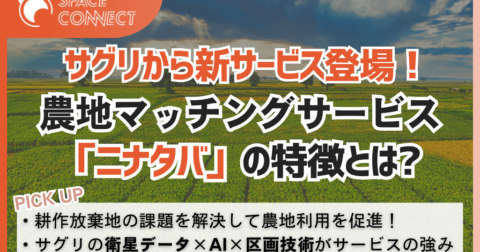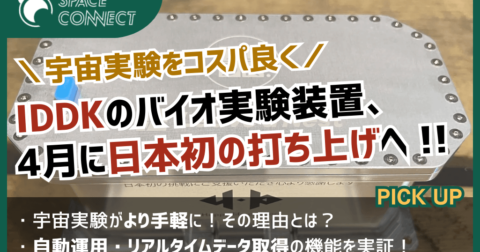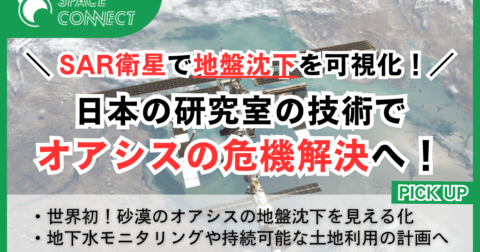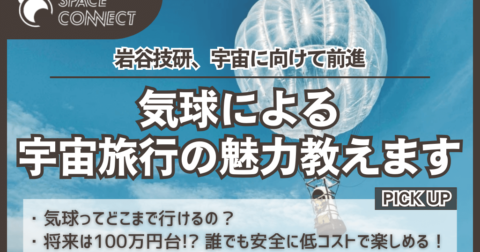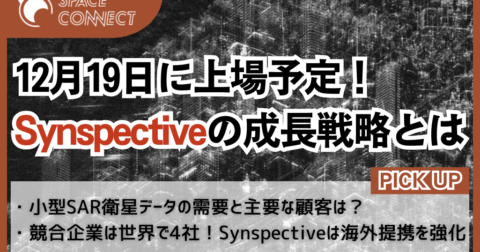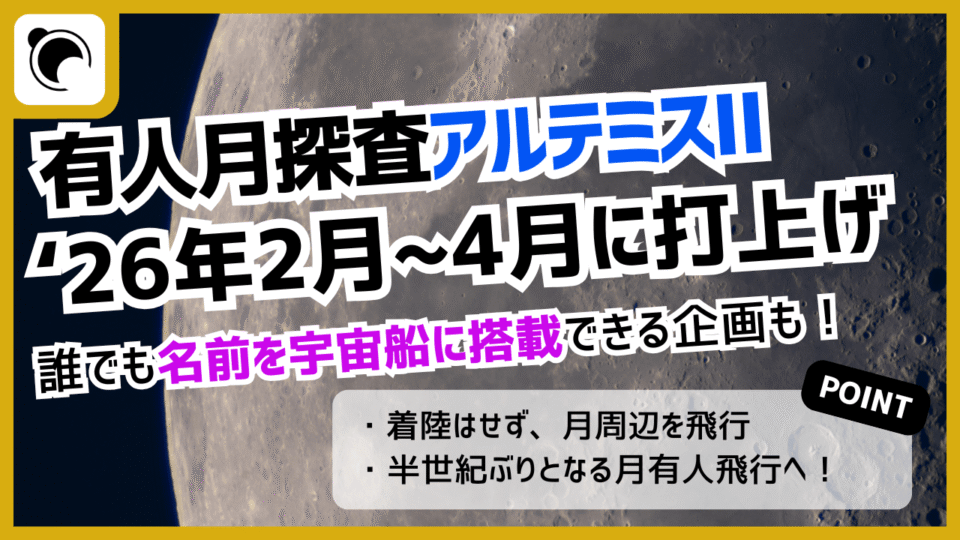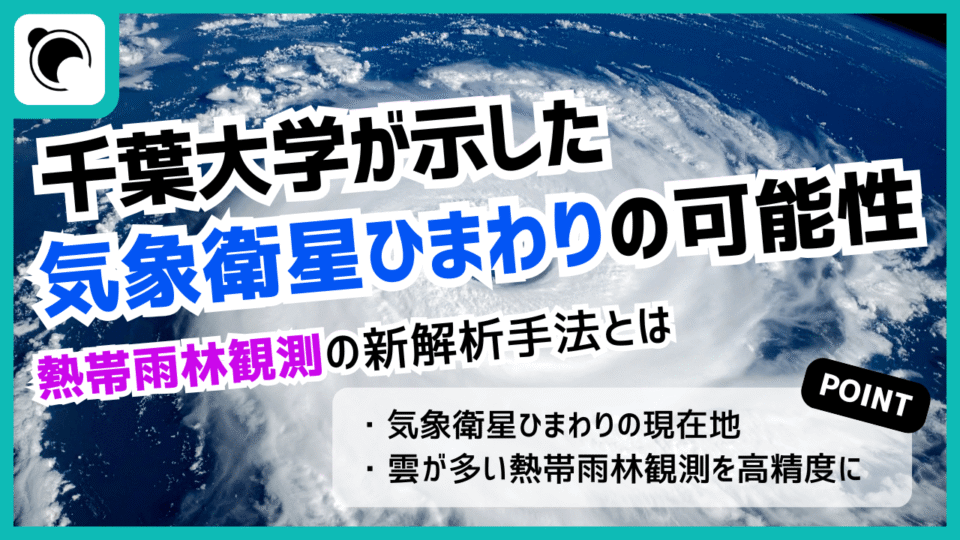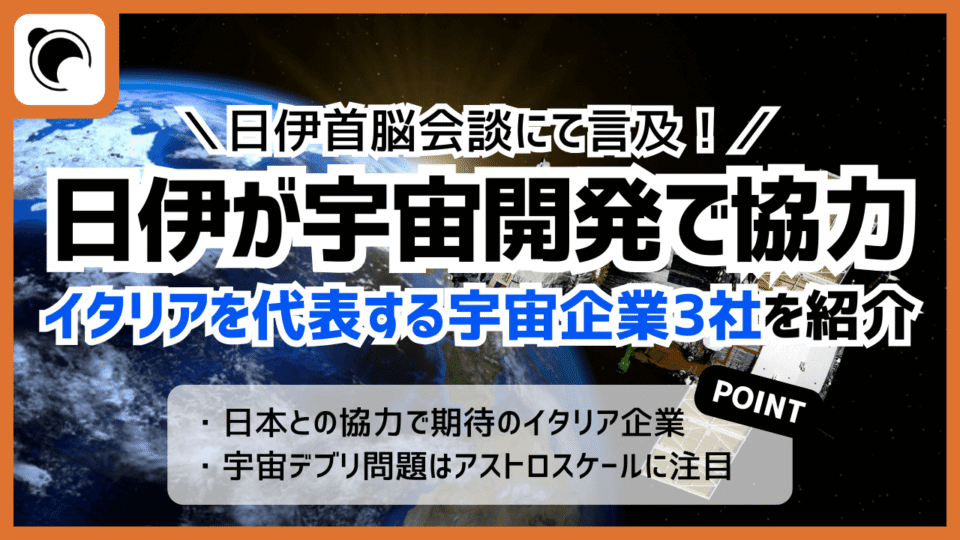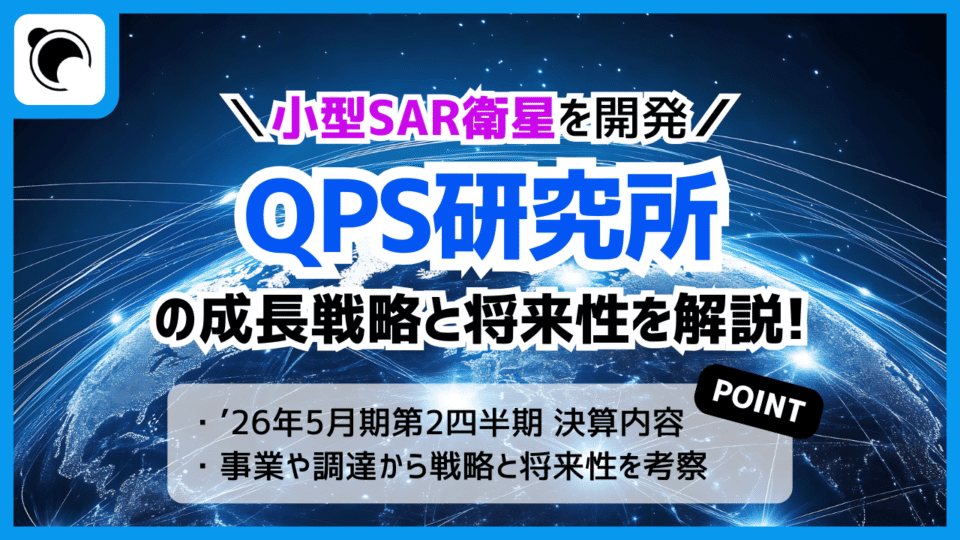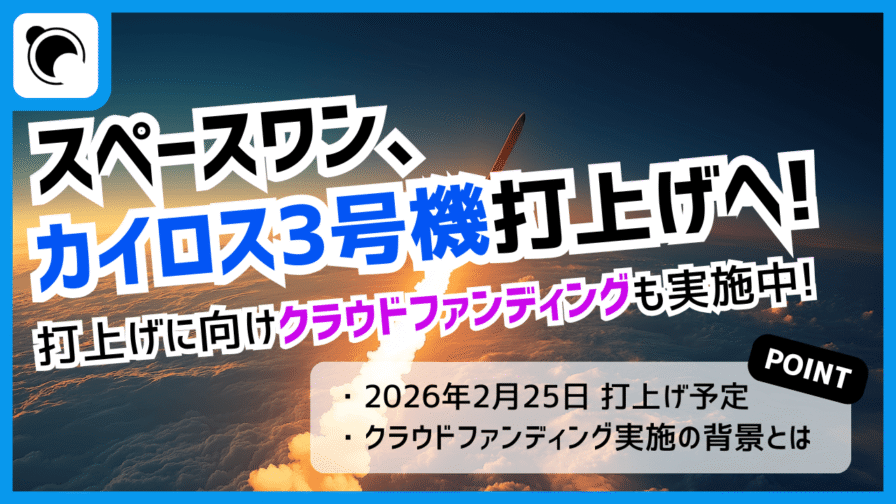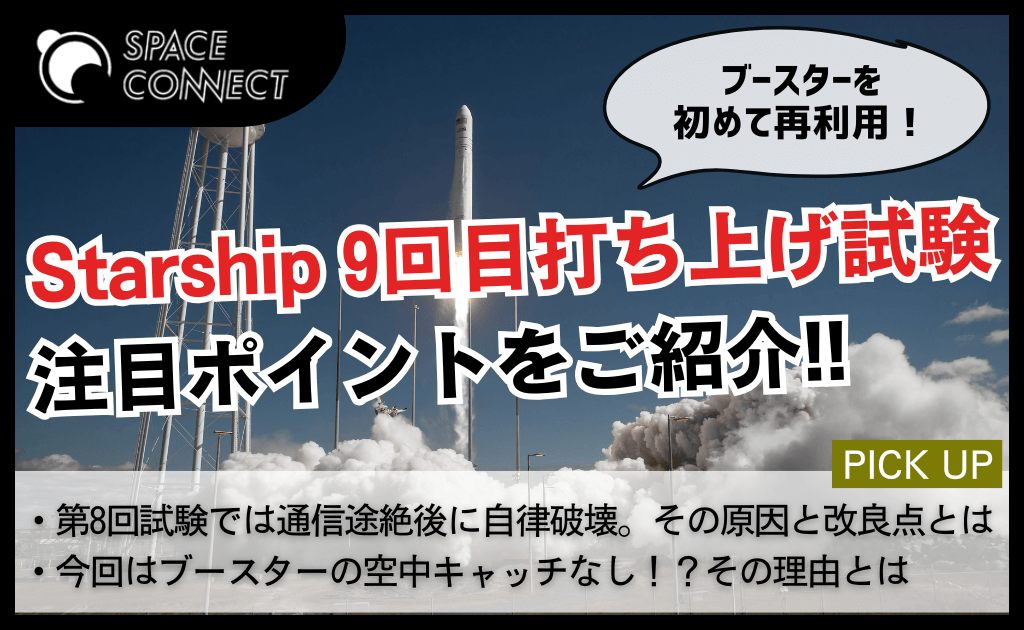
スペースXが開発する超巨大ロケット「スターシップ(Starship)」の第9回打ち上げ試験が、2025年5月28日午前8時30分(日本時間)以降に予定されている。(2025/5/27 7:00時点の情報)
本記事では、前回の試験結果を振り返り、特に上段のスターシップ宇宙船が通信途絶に至った原因を詳しく解説するとともに、今回の打ち上げ試験の目的やミッションの注目ポイントについてご紹介する。
目次
スターシップの概要
スペースXが開発している超大型ロケット「スターシップ」は、人や貨物を地球周回軌道や月、火星、深宇宙まで運ぶために設計された、史上最大のロケットだ。
下段の「スーパーヘビー(Super Heavy)」ブースターと上段の「スターシップ」宇宙船で構成されている。
大きな特徴は以下の2つ。
- 史上最大の大きさと打ち上げ能力
- 完全再利用可能で一日に複数回打ち上げ
まず、ロケット「スターシップ」は全長約123メートルを誇り、およそ100~150tものペイロードを運ぶ能力を持つ。
最大100人の乗組員と貨物を輸送可能であり、月面基地の建設や火星探査、また地球上のどの場所でも1時間以内で移動するための輸送手段として期待されている。
次に、同ロケットは完全かつ迅速な再利用が可能となるように開発されている。
従来の一般的なロケットは一度打ち上げられるとその多くの部分が使い捨てられるが、スターシップはブースター、宇宙船ともに再利用可能となる。機体を繰り返し使用することで打ち上げコストの大幅な削減を目指している。
そして、一度使用して返ってきた機体はすぐに点検・打ち上げ準備を完了させて再度打ち上げる。飛行機のように着陸・打ち上げ(離陸)をスムーズに行うことで、将来的には一日あたり複数回、人や貨物を宇宙または地球上のどこかに輸送することを目指しているのだ。
前回(第8回)の打ち上げ試験結果と分析
2025年3月に実施されたスターシップの第8回打ち上げ試験では、第7回打ち上げ試験での空中分解事故を受け、スターシップ宇宙船のハードウェアや運用システムに改良が施された状態での再挑戦となった。初のペイロード展開試験やスターシップ宇宙船の帰還技術の実証、ブースターの空中キャッチ再挑戦を目指していた。
結果として、下段のスーパーヘビーブースターは3度目の空中キャッチに成功し、再使用を目指す上での大きな成果をあげた。一方で、上段のスターシップ宇宙船は飛行開始から約9分半後にすべてのエンジンが停止し、通信が途絶。その直後に自律飛行安全システムが作動し、機体が安全に破壊されたと見られている。
この章では、上段の宇宙船と下段のブースターそれぞれについて、第8回打ち上げ試験結果とその分析の詳細をご紹介していく。
スーパーヘビー:3度目の空中キャッチに成功
スターシップ第8回打ち上げ試験では、スーパーヘビーブースターに搭載された33基のラプター(Raptor)エンジンはすべて正常に始動し、機体は順調に上昇を開始した。
スーパーヘビーは上昇中に1回目の燃焼を終え、中央3基を除くエンジンを停止。その後、一段目の分離直前から二段目のエンジンを起動する「ホットステージング」操作を実施し、スムーズに分離が行われた。
分離後、スーパーヘビーは姿勢と速度を調整しながら、空中キャッチを目指して発射場への帰還を開始した。正常に再点火されないエンジンも一部あったが、それでもスーパーヘビーブースターとして3回目となる空中キャッチに成功した。
スペースXは、再点火されなかったエンジンの原因について、点火装置周辺の温度条件によって点火に支障がでた可能性が高いと分析。
地上試験で問題の再現に成功しており、今後はエンジンに追加の断熱材を導入することで、再発防止を図るとしている。
スターシップ:通信途絶し自律破壊へ
上段のスターシップ宇宙船は、スーパーヘビーブースターからの分離後、予定の軌道を飛行した。
しかし、スターシップ宇宙船のエンジン燃焼開始から約5分半後、機体後部にある中央3基のエンジンのうち1基の周辺で閃光が観測され、激しい衝撃が発生して同エンジンが停止。続いて、中央エンジン2基を含めた3基のエンジンも停止し、スターシップは制御を失った。
その後、最初の閃光観測から約2分後に通信が途絶。最終的に受信されたデータでは、すべてのエンジンが停止していたことが確認された。
スペースXは、通信途絶の直後に自律飛行安全システムが作動し、機体が破壊されたと見ている。実際、通信が途絶えた後、スターシップは大気圏に再突入して分解する様子が観測されている。
事故発生後、スペースXは直ちに米連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)などと連携し、緊急時の対応や残骸の回収・清掃活動を実施。残骸は事前に設定された「残骸対応区域」内に落下しており、有害物質は含まれておらず、海洋生物や水質への重大な影響もないとしている。
今回の事故の原因とされるのは、中央ラプターエンジン1基のハードウェア故障による、予定されていない燃料の混合や点火。スペースXはこの問題の解明に向けて、100回を超える地上試験を実施しており、今後はより信頼性を高めたラプターエンジンを導入する方針だ。
なお、この事故は第7回打ち上げ試験における空中分解と同様の段階で発生しているが、同社は「原因は明確に異なる」と説明。第7回打ち上げ試験後に改良されたエンジンシステムは、第8回打ち上げ試験では正常に機能していたと報告されている。
第9回打ち上げ試験のポイント
第8回打ち上げ試験を踏まえ、スペースXは不具合の原因分析を完了し、スーパーヘビーブースターおよびスターシップ宇宙船それぞれにハードウェアの改良を施した。
そのうえで、第9回打ち上げ試験では、スーパーヘビーが新たな挑戦に臨む一方、スターシップ宇宙船は前回未達成だったミッションに再挑戦する。
今回の主な注目ポイントは以下の3つ。
- スーパーヘビー:初の再利用による打ち上げ
- スーパーヘビー:推進剤節約を目指した新たな降下技術の検証
- スターシップ:模擬衛星の展開や再突入技術の再評価
スーパーヘビー:初の再利用による打ち上げ
今回使用されるスーパーヘビーブースターは、第7回打ち上げ試験にて回収されたものであり、過去の打ち上げで飛行実績を持つ機体の再使用としては初の試みとなる。
スーパーヘビーは、将来的に「1日複数回打ち上げ」を視野に入れた開発が進められており、この再使用技術はその中核をなす。
この試験のため、第7回打ち上げ試験で打ち上げられたブースターは回収後に広範な検査が実施され、メンテナンスまたは交換が必要な箇所が特定された。
いくつかの使い捨て部品は交換したが、33基のラプターエンジンのうち29基を含む、主要なコンポーネントは再使用となる。
そしてこのブースターでは、次章で説明するように、将来の打ち上げ能力や緊急対応を見据えた試験も予定されている。
スーパーヘビー:推進剤節約を目指した新たな降下技術の検証
スーパーヘビーブースターの分離後には推進剤搭載量の削減等のため、以下の3つの技術がテストされる。推進剤の消費を最小限に抑えることができれば、その分の余剰をペイロード(衛星などの輸送物)に割り当てることが可能となる。
- 分離後、エンジンの逆噴射を行う前に機体が反転する方向を制御
- 大気の抵抗がより大きくなるような角度で降下
- 着陸時に使用するエンジン数の減少
まず、スーパーヘビーとスターシップの分離時には、従来のようにスターシップのエンジン点火時に生じる推力のわずかな差によりランダムな方向に反転するのではなく、あらかじめ決められた方向に反転するよう制御される。
具体的には、機体の通気口をいくつか塞ぐことで、スターシップのエンジン推力がブースターの既知の方向へ押し出す構造となっている。
この制御を行うことで、姿勢制御などに使用される予備燃料の搭載量を削減できるため、上昇中により多くの燃料を使用し、その結果としてより多くのペイロードを宇宙に運ぶことができる。
次に、スーパーヘビーは降下中、従来よりも大きな迎角(気流に対する機体の傾き)で飛行する。これにより、空気抵抗が増加し、降下速度が抑えられるため、着陸前の減速に必要な推進剤の量を削減することができる。
今回の打ち上げ試験では、この高迎角状態における機体の制御性能について、実機からのデータを取得する狙いがある。
さいごに、着陸時のエンジン数を意図的に制限する試験も実施される。
従来は3基の中央エンジンで着陸噴射を実施していたが、今回は1基をあえて停止し、代わりにバックアップのエンジンが機能するかを確認。その後、中央2基のエンジンのみの噴射に切り替え、アメリカ湾上空で停止し、着水する予定だ。
また今回、スーパーヘビーブースターがアメリカ湾上空に着水するのは、初めて実施される一連の実験が発射場に与えるリスクを考慮した措置である。発射場の安全性を確保するため、これらの実験はアメリカ湾岸沖の軌道上で実施され、スーパーヘビーの空中キャッチは行われない予定となっている。
スターシップ:模擬衛星の展開や再突入技術の再評価
上段のスターシップ宇宙船は、前回達成できなかった複数のミッションに再挑戦する。
まずは、次世代スターリンク衛星と同規模の模擬衛星8基の展開である。これは、スターシップ本体と同じ弾道軌道(地球を周回しない軌道)を通過し、大気圏再突入時に消失する設計となっている。
さらに、宇宙空間でのラプターエンジン1基の再点火も予定されており、上段ロケットの軌道上再始動能力の確認が試みられる。
加えて、将来的にスターシップを発射場へと帰還させるための重要な技術検証も行われる。 機体表面から多数の耐熱タイルを意図的に取り外し、再突入時における脆弱部位のストレステストを実施するほか、能動冷却機能を備えたものを含む複数種の金属タイルを搭載し、再突入に耐え得る代替素材の有効性を評価する。
また、機体側面にはキャッチ試験を見据えた構造が取り付けられており、これらの熱性能や構造耐久性も検証される。第6回打ち上げ試験にて再突入時に観測された過熱箇所(ホットスポット)への対策としては、機体全体のタイルの端部を滑らかにテーパー加工することで、局所的な熱集中を緩和する工夫が加えられている。
開発段階の飛行試験は、その性質上、常に予測困難な要素をはらんでいる。しかし、現実の飛行環境でできる限り多くの試験を重ねることこそが、完全かつ迅速に再利用可能な宇宙船の実現に向けた最短ルートだとスペースXは考えている。
さいごに
いかがでしたか。
スターシップの打ち上げ試験は、毎回が「成功か失敗か」ではなく、どれだけ多くの知見を次につなげられるかという観点で評価されるべきフェーズにある。
第9回打ち上げ試験では、前回の課題を受けた具体的なハードウェア改修と、より実運用に近い技術検証が数多く盛り込まれている。
LIVE配信は、スペースXのHPまたはXアカウントにて視聴できる。
今回の打ち上げにも注目だ。